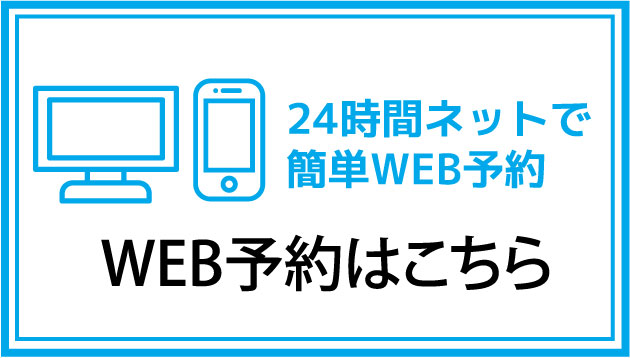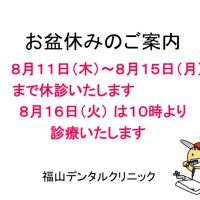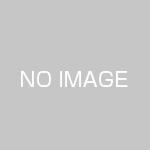インプラント周囲炎の初期症状・進行した症状と治療法&予防法
インプラント周囲炎とは、インプラントを支える歯茎や骨に炎症が生じ、放置するとインプラントが脱落する恐れがある疾患です。
初期症状は軽度の腫れや出血などですが、進行すると骨が破壊され、痛みや膿が発生することもあります。
この記事では、インプラント周囲炎の症状や進行過程、原因、治療法、予防策について詳しく紹介します。
インプラントを長く維持するために、適切なケアを知り、トラブルを未然に防ぎましょう。
インプラント周囲炎とは
インプラント周囲炎は、インプラントを支える歯茎や顎の骨に炎症が生じる疾患です。
細菌感染が主な原因とされ、初期には軽度の腫れや出血などの症状が現れますが、進行すると膿が出たり、顎の骨が吸収されることがあります。
最終的にはインプラントが支えを失い、脱落する危険性もあるため、症状に気付いたら早めのケアが必要です。
特に、口腔ケアが不十分な場合や、もともと歯周病のリスクが高い人は発症しやすい症状であり、日頃から十分な対策が求められます。
症状が軽いうちに適切な処置を行うことで進行を防止しやすいため、気になる症状を感じたら、できるだけ早めに歯科医院を受診しましょう。
インプラント周囲炎の初期症状や進行すると見られる症状

インプラント周囲炎は、初期段階では自覚症状がほとんどありません。しかし、放置すると炎症が広がり、インプラントの安定性が損なわれることもあります。
ここでは、初期に現れる兆候、症状が進行した場合の変化、治療を行わずに放置した場合のリスクなどについて紹介します。
インプラント周囲炎の兆候
インプラント周囲炎の初期症状は軽度なものが多く、気付きにくいことがあります。主な兆候としては以下が代表的です。
- 歯茎の腫れ・赤み
- 歯磨き時の出血
- インプラントの周囲に違和感 など
炎症が軽度なうちに適切なケアを行うことで、症状の悪化を防ぎやすくなるため、違和感や出血が続く場合は放置せずに歯科医院を受診し、専門的なケアを受けることが重要です。
定期的な検診を受けることで、インプラントを健康な状態に維持しやすくなります。
進行した場合に見られる症状
インプラント周囲炎が進行すると、口腔環境が悪化し、異常が目立つようになります。特に以下の症状が出ている場合は要注意です。
- 腫れや出血が悪化した
- 歯茎から膿が出た
- 口臭が強くなった
- インプラントがぐらつくようになった
このような症状が現れた場合、インプラント周囲炎がすでに悪化している可能性が高く、放置するとインプラントの脱落につながりかねません。気付いたら早めに歯科医院で相談しましょう。
治療せずに放置した場合
インプラント周囲炎を治療せずに放置すると、顎の骨が徐々に破壊され、インプラントが支えを失う可能性があります。
炎症が広がると痛みが強くなり、日常生活にも影響を及ぼしてしまうことも多くなるでしょう。
さらに進行するとインプラントが完全に脱落し、インプラントの再治療が困難になる可能性もあります。
歯の脱落は食生活や会話に悪影響を及ぼし、生活の質を落とす原因です。快適な生活を楽しむためにも、適切な対策を取り、インプラント周囲炎を防ぎましょう。
インプラント周囲炎になる原因
インプラント周囲炎はさまざまな要因によって発症しますが、口腔内の衛生状態や既存の歯周病、生活習慣の影響が大きいとされています。
また、持病や歯科医師の技術、噛み合わせの問題が関わるケースにも注意が必要です。
ここでは、インプラント周囲炎を引き起こす主な原因について紹介します。
口腔ケアの不足
インプラントは細菌に対する防御機能が低いため、適切なケアを怠ると細菌が付着しやすくなります。
インプラント周囲の清掃が行き届かないと、細菌が増殖しやすくなり、初期段階では軽い腫れや出血が見られることがあります。
例えば、歯磨きが不十分な場合はプラークが溜まり、炎症を引き起こしやすくなってしまいがちです。
時間経過とともに炎症が悪化し症状が進行するため、日常的に適切なケアを心がけましょう。
もともとあった歯周病の影響
歯周病が完治していない状態でインプラント手術を行うと、細菌感染のリスクが高まります。歯周病は歯茎や骨にダメージを与えるため、インプラントを埋入する土台が不安定になりやすいのです。
さらに、細菌がインプラント周囲に残っていると、手術後に炎症が起こりやすくなります。
もともと歯周病を患っていた場合は、事前に適切な治療を受けて完治させ、炎症の原因を取り除いたうえでインプラント治療を進めるようにしましょう。
歯周病を患っている場合は事前の検査で分かることがほとんどですが、心当たりがある患者さんは、先に歯科医師へ話しておくとスムーズな検査や治療を進めやすくなります。
喫煙習慣
喫煙はタバコに含まれる有害物質が歯茎の血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、細菌感染が起こりやすくなります。
また、傷の治癒を妨げる作用もあるため、手術後の回復が遅れる可能性があり、喫煙する患者さんも手術の前後は禁煙・節煙をおすすめします。
喫煙者は非喫煙者よりもインプラント周囲炎を発症する確率が高いとされており、インプラントの安定性を保つためには、禁煙や適度な節煙が必要になるでしょう。
貧血
貧血によって血液の循環が悪くなると、インプラント周囲の組織に十分な酸素や栄養が行き渡らず、炎症が起こりやすくなります。
特に鉄分が不足している場合は、歯茎の健康状態が悪化しやすく、細菌への抵抗力も低下するため、インプラント周囲炎のリスクが高まりやすいです。
貧血を防ぐためには、鉄分を多く含む食品(レバー、赤身肉、ココアなど)を積極的に摂取することをおすすめします。
また、重度の貧血を抱えている場合は無理をせず、先に歯科医師と相談し、適切な対応を取りながらインプラント治療を進めて行く必要があります。
持病(糖尿病)
糖尿病を抱えている場合、血糖値のコントロールが不十分だと免疫機能が低下し、細菌感染が起こりやすくなります。
その影響でインプラント周囲の組織が炎症を起こしやすくなり、周囲炎のリスクが高まる恐れがあります。
また、傷の治癒も遅くなるため、手術後の回復に時間がかかることが少なくありません。血糖値が安定している状態でインプラント治療を受けることが望ましいです。
糖尿病の治療を受けている主治医とも相談し、歯科医院と連携を取りながらインプラント治療計画を立てるようにしてみてください。
医師の技術不足
インプラント治療は高度な技術が必要であり、歯科医師の経験や技術が不足していると、術後のトラブルにつながる可能性が否定できません。
不適切な埋入位置・過度な負荷がかかる治療計画などは、インプラント周囲の組織に負担がかかり、炎症のリスクが高まります。
さらに、術後のメンテナンスが適切に行われない場合には細菌感染が進行する恐れもあるため、インプラント治療を受ける際は、経験豊富な歯科医師を選ぶことが重要です。
当院では経験豊富な医師がインプラント治療を担当しています。治療計画や技術面でご不安があれば、事前にどんな小さなことでもご相談・ご確認ください。
歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりがあると、インプラントに過剰な負荷がかかり、周囲の骨や歯茎にダメージを与えることがあります。
特に就寝中の歯ぎしりや食いしばりは無意識に強い力が加わるため、インプラントが破損したり、安定性が損なわれたりする原因になります。
長期間にわたって強い負荷がかかるとインプラントの寿命が短くなり、最悪の場合、インプラントが脱落することもあります。
このようなトラブルを防ぐために、歯ぎしりや食いしばりの対策をしましょう。
歯科医院では歯ぎしり・食いしばり対策に役立つナイトガード(マウスピース)などを用意しています。気になる人は相談してみてください。
インプラント周囲炎の治療方法
インプラント周囲炎の治療は、炎症の進行度に応じて異なっています。
軽度の場合は歯垢や歯石の除去、適切な炎症ケアが中心となりますが、重症化すると外科的な処置が必要になる可能性も否定できません。
ここでは、インプラント周囲炎の代表的な治療方法について紹介します。
歯垢の除去
インプラント周囲炎の治療では、細菌の温床となる歯垢や歯石を除去することが基本です。専用の器具を用いてインプラントの表面を清掃し、細菌の繁殖を抑えます。
通常の歯ブラシでは除去しきれない汚れも、超音波スケーラーや専用のクリーニング器具を使うことで効果的に取り除けます。
初期段階で適切なクリーニングを行うことで炎症の進行を抑え、インプラントの安定性を保ちやすくなるでしょう。
炎症ケア
炎症が確認された場合は、抗菌剤の使用や殺菌効果のある薬剤での洗浄を行います。これにより細菌の増殖を抑え、炎症の拡大を防ぐことが目的です。
また、軽度のインプラント周囲炎であれば、部分的な薬剤の塗布や消毒を継続することで症状が改善することも期待できます。
炎症が長引くと骨への影響も懸念されるため、適切な処置が必要です。
外科的な治療が選択されることも
前述のような内科的治療をしても改善が見られない場合、外科的治療が行われる可能性が高いです。以下のような治療方法が検討されます。
- 歯茎の切開
- インプラントに付着した汚れ・プラークを除去
- 場合によっては炎症部位の除去も検討
また、インプラントが土台で支えられず、ぐらつきが出ている場合、インプラントそのものを除去することもあります。
顎の骨が残っていればまたインプラント治療ができることが多いですが、個人の状態や歯科医師の方針によってはその限りではありません。
再治療が不可能にならないように、インプラント周囲炎の兆候を見逃さず、可能な限り早く治療を開始しましょう。
インプラント周囲炎予防のためにできるケア

インプラントを長く使うためには、日常生活の中でできる意識的なケアや習慣が大切です。
特に、定期的な歯科検診や丁寧な口腔ケア、喫煙習慣の見直しがインプラント周囲炎のリスクを軽減しやすくなるでしょう。
ここでは、インプラントを健康に保つための具体的な予防策について紹介します。
歯科医院で定期検診を受ける
インプラントを長持ちさせるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。
定期検診では主に以下のようなことを行います。
- インプラント周囲のプラークや歯石を除去
- 炎症の有無をチェック
- インプラント本体の状態を確認
インプラントは天然歯とは異なり、歯根膜がないため、異常が発生しても自覚症状が現れにくいです。
定期的な検診を受けることにより、インプラント周囲炎の早期発見につながり、必要に応じた治療をスタートしやすくなるでしょう。
特に歯周病の既往歴がある場合はリスクが高いため、より慎重なケアをおすすめします。
口腔ケアを徹底する
日常的な口腔ケアは、インプラントの寿命を左右する重要な習慣です。
歯ブラシだけではなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使用し、インプラント周囲の汚れを徹底的に除去するようにしましょう。
歯磨き時の力が強すぎると歯茎を傷つけることがあるため、適切な圧力で磨きましょう。定期検診で適切な歯の磨き方について指導を受けるのもおすすめです。
ほかにも抗菌作用のある洗口液を使用し、細菌の増殖を抑える対策も取り入れてみてください。
日々のケアを丁寧に行うことで、インプラント周囲炎のリスクを低減できます。
禁煙する
禁煙することによって歯茎の健康を維持し、インプラントのトラブルを防ぎやすくなります。
喫煙はインプラント周囲炎のリスクを高める要因のひとつです。タバコに含まれる有害物質が歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、細菌感染を引き起こしやすくなります。
また、喫煙者はインプラント手術後の傷の治癒が遅れることがあります。治療完了までの期間を短くし、快適な口腔環境を整えるためにも、インプラント手術の際は禁煙や節煙を心がけましょう。
まとめ
インプラント周囲炎は初期症状が分かりづらく、気が付くと進行してしまっていることが多い症状です。
日頃のケアの徹底や歯科医院での定期検診、禁煙・節煙など、インプラント周囲炎の予防に効果的な生活習慣を取り入れることも検討してみてください。
インプラント周囲炎にかかり、そのまま放置しておくと、最悪の場合はインプラントの脱落につながりかねないため、もしも異常を感じたらすぐに受診することをおすすめします。
福山デンタルクリニックではインプラント周囲炎を予防するための定期検診や歯磨き指導、日頃のケアのご相談など、幅広く対応しています。インプラント周囲炎が気になる患者さんはぜひ一度ご相談ください。