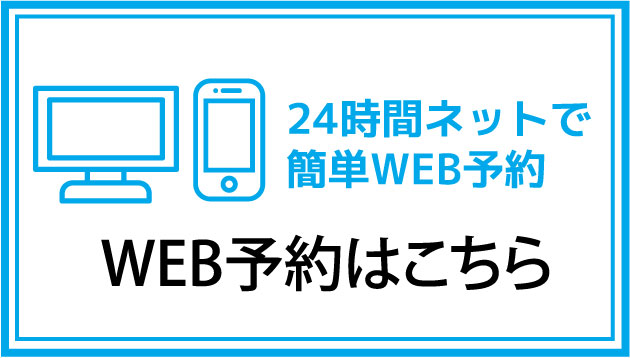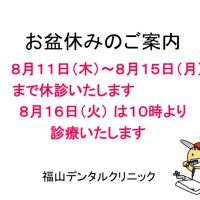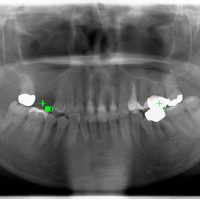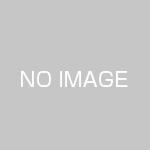インプラントの医療費控除手続きの流れ・還付金目安・条件を解説

インプラント治療は高額になりやすく、費用面で悩みが生まれがちです。しかし、医療費控除を活用できるケースもあるため、税負担の軽減が期待できることもあります。
ただし、インプラント治療のすべてが控除対象になるわけではありません。また、適用条件や申告手続きについて理解しておくことが重要です。
この記事では、インプラントの医療費控除が適用される条件、申告手続きの流れ、還付金の目安などを詳しく紹介します。
控除を最大限活用するために、事前に必要な書類の準備や計算方法も確認し、スムーズに手続きを進めましょう。インプラントの医療費控除に興味がある人は、ぜひ参考になさってください。
医療費控除とは
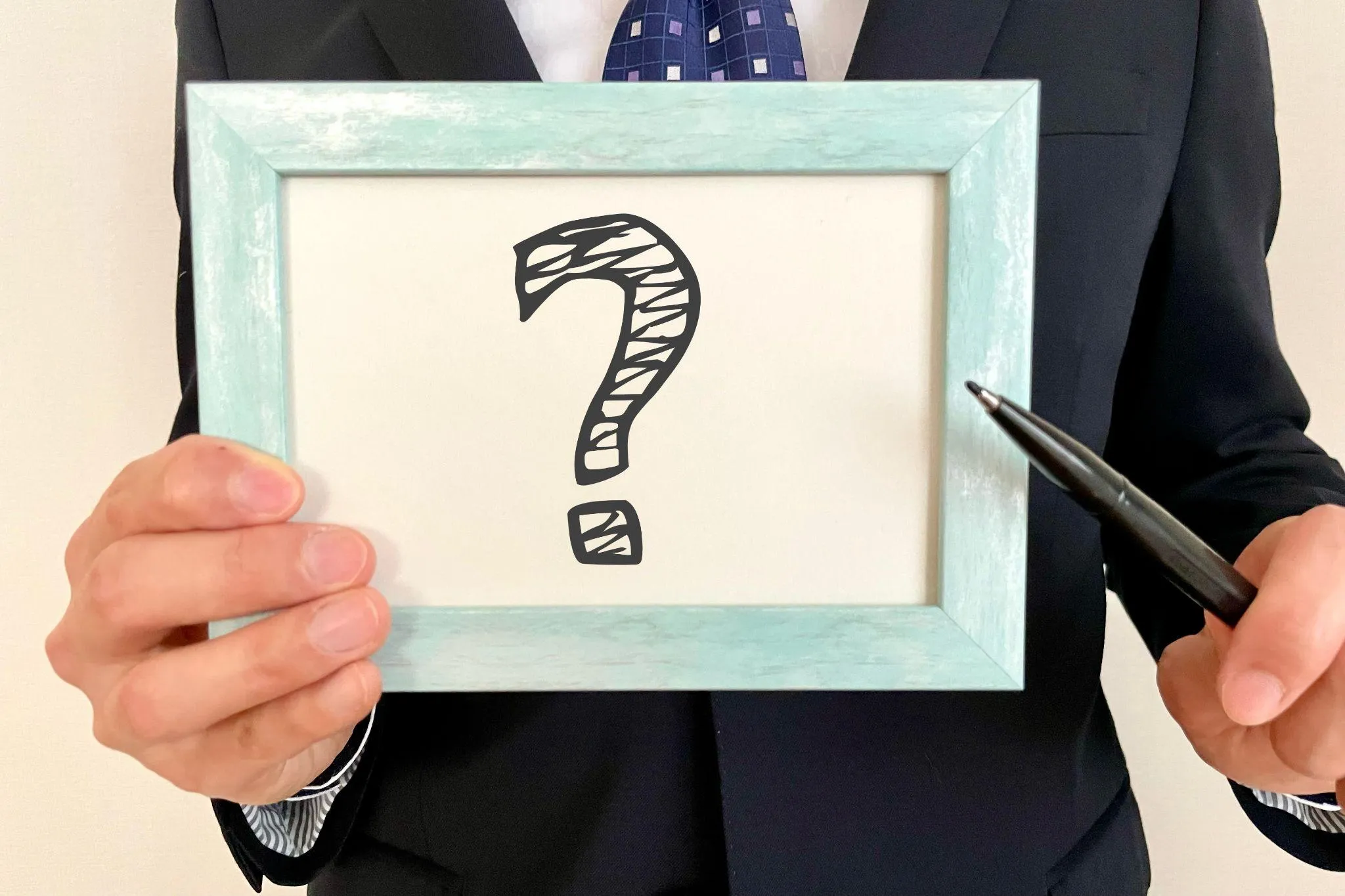
医療費控除とは、納税者が自分や生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超える場合、所得からその超過分を差し引くことができる制度です。
ここでは、医療費控除の基本について紹介します。
医療費控除の概要
医療費控除は、年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得からその超過分を控除できる制度で、控除額の上限は200万円になります。
具体的には以下のような仕組みです。
| 総所得金額に関して | 控除対象になる部分 |
|---|---|
| 総所得金額等が200万円以上 | 10万円を超える部分が控除対象 |
| 総所得金額等が200万円未満 | 総所得金額等の5%を超える部分が控除対象 |
対象となる医療費は、納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者や親族のために支払ったものも含まれます。
また、一定の条件を満たしていれば、治療のための通院費や医療用器具の購入費用なども控除の対象です。
ただし、美容目的の歯列矯正や予防接種など、治療以外の目的で支払った費用は対象外となるため、注意が必要です。
控除手続きは確定申告で行う
医療費控除を受けるためには必ず確定申告が必要であり、給与所得者の年末調整では対応できません。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間申告が可能になっています。
領収書は必ず保管しておくこと
医療費控除の申告を行う際、医療費の領収書は大切な関係書類です。税務署からの問い合わせや確認があった場合に備え、領収書は5年間保管しておく必要があります。
医療費の明細書や領収書などの提出が求められることがあるため、申告予定のある人は必ず保管しておきましょう。
医療費通知を活用することで、明細書の記入を簡略化できる場合もありますが、領収書自体の保管義務が免除されるわけではありません。
インプラントで医療費控除の対象になる条件

インプラント治療は高額になることが多いため、医療費控除を活用することで税負担を軽減できます。
しかし、すべてのインプラント治療が控除対象となるわけではなく、適用されるための条件が定められている点には注意が必要です。
ここでは、医療費控除の対象となる具体的な条件を解説します。
『噛む機能』のための治療である
インプラント治療が医療費控除の対象となるためには、失った歯の機能を回復し、噛む機能を取り戻すことを目的とした治療である必要があります。
例えば、虫歯や歯周病などで歯を失った場合、その機能を補うために行われるインプラント治療は医療費控除の対象です。
一方、審美的な目的、つまり見た目を良くするためだけのインプラント治療は、医療費控除の対象外になります。
あくまで目的が『噛むための機能』の回復で、生活の質を向上させるための治療であることが重要であり、審美性を高める治療については考慮されません。
医療費が年間10万円以上
医療費控除を受けるためには、その年(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が10万円以上であることが必要です。
ここで注意すべき点は、インプラント治療の費用だけでなく、生計を共にする家族全員の医療費を合算して10万円以上であれば、控除の対象となるということです。
例えば、本人の医療費が6万円、家族の医療費が4万円であれば、合計10万円となり、医療費控除の対象となります。
なお、総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%を超える部分が控除対象です。
このような条件を満たすことで、インプラント治療にかかった費用を医療費控除として申告することが可能となり、税負担の軽減が期待できます。
インプラント医療費控除の注目点

インプラント治療は医療費控除で税負担の軽減が可能ですが、それに加え、いくつかの注目しておきたい点があります。
ここでは、控除額をできる限り活用するための注目点について紹介します。
本人以外も控除対象になる可能性がある
医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を共にする家族・親族の医療費も対象になります。ただし、生計を共にしていることが前提となるため、確定申告の際には以下の点に注意が必要です。
- 別居している場合は原則として対象外
- ただし別居している本人が申告者からの仕送りで生活している場合は対象になる
- 申告者が医療費を払った場合も対象になる
対象になる家族・親族の治療費をまとめて申告することで、控除額を大きくできるケースもあるため、家族全員の医療費を把握しておくとよいでしょう。
デンタルローンやクレジットカード払いでも申告可能
インプラント治療費をデンタルローンやクレジットカードで支払った場合でも、医療費控除の対象となります。
ただし、確定申告で医療費控除の対象になるのは実際にその年に支払った金額のみになります。
例えば、総額60万円のインプラント治療を3年ローンで支払い、年間20万円ずつ返済する場合、その年の医療費控除の対象となるのは20万円分のみという考え方です。
また、控除の対象になるのは治療費そのものであり、ローンの金利やクレジットカードの分割払い・リボ払いなどの手数料は対象外になるため、確定申告の際には注意しましょう。
所得の多い人が申告するとお得
医療費控除は、支払った医療費の一部が所得控除として適用され、所得税の負担を軽減する仕組みです。
このため、同じ医療費を申告する場合でも、所得が多い人が申告すると、より大きな節税効果を得られる可能性があります。
所得税率は累進課税制度に基づいて計算されるため、所得が高いほど税率も上がる仕組みです。
例えば、所得税率が20%の人と10%の人が同じ金額の医療費を控除申請した場合、還付される金額は所得税率の高い人のほうが多くなります。
5年前までさかのぼって申告できる
その年の確定申告で申請しなくても、過去5年以内であれば遡って医療費控除の申告が可能です。以下のような場合も改めて申告してみてください。
- 確定申告を忘れていた
- 過去のインプラント治療費が医療費控除の対象であることを後から知った
例えば、3年前にインプラント治療を受け、医療費控除を申請していなかった場合でも、今年の確定申告で遡って申告することで還付金を受け取れる場合があります。
申告の際には、過去の領収書や診療明細書を整理し、申告漏れがないようにしましょう。なお、還付申告の場合は通常の確定申告とは異なり、1月から手続きを行うことが可能です。
通院にかかった交通費も一部申告可能
インプラント治療のために通院した際の交通費も、医療費控除の対象になる場合があります。
ただし、対象となるのは公共交通機関(電車やバスなど)の交通費であり、自家用車のガソリン代や駐車料金は含まれません。
通院にかかった交通費を控除するためには、治療のための移動であったことを証明できるように、通院日や交通費の金額を記録しておくことが重要です。
通院の際に交通費を記録し、ICカードの利用履歴や領収書を保管しておくと、申告時に手間を省きやすくなるでしょう。
なお、タクシー料金については、緊急時ややむを得ない場合(公共交通機関が利用できない事情があるなど)のみ認められる可能性があるため、不明な点は税務署に問い合わせてみてください。
インプラントの医療費控除手続きの流れ

インプラント治療の医療費控除は確定申告が必要です。ここでは、医療費控除の手続きについて、必要な書類や具体的な手続きの流れについて紹介します。
事前に必要な書類を用意しておく
医療費控除を受けるためには、医療費や交通費の領収書など、治療に必要な費用であったことを証明する書類が必要です。
以下の書類を確定申告前に準備しておきましょう。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 医療費の領収書 | 治療を受けた歯科医院から発行された領収書 |
| 通院にかかった交通費の記録 | 公共交通機関を利用した場合、その利用区間や金額が分かる領収書 |
| 医療費控除の明細書 | 医療費の詳細を記載する明細書 |
| 医療費通知(医療費のお知らせ) | 加入している健康保険組合から送付される医療費の通知書 |
| 源泉徴収票 | 給与所得者の場合、申告手続きに勤務先から発行される源泉徴収票が必要 |
| 本人確認書類 | 確定申告者の本人確認ができる証明書。運転免許証・マイナンバーカードなど |
なお、2017年分の確定申告から、医療費控除の申請時に領収書の提出は不要となり、『医療費控除の明細書』の提出が必要となりました。
ただし、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
手続きの流れ
確定申告の提出期間は、通常、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間申告が可能になっています。
確定申告の際、まずは以下の流れで申請書類を作成しましょう。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 【1】医療費の集計 | 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費を集計する
生計を共にする家族の医療費も合算可能 |
| 【2】医療費控除の明細書作成 | 集計した医療費の内容を『医療費控除の明細書』に記載する |
| 【3】確定申告書の作成 | 医療費控除額を計算し、確定申告書に必要事項を記入する |
| 【4】申告書の提出 | 作成した確定申告書と医療費控除の明細書を、所轄の税務署に提出する |
提出の際は所轄の税務署に直接持参するか、郵送で提出しますが、昨今は『e-Tax』を利用したオンライン申告も可能です。
医療費控除の計算方法と還付金の目安

医療費控除を申請した場合、還付金はどれくらいになるのでしょうか。ここでは、医療費控除の計算方法と還付金の目安について紹介します。
あくまで目安のため、実際の金額とは多少異なる可能性がありますが、参考のひとつにしてみてください。
医療費控除の計算方法
医療費控除額は以下の式で計算されます。民間保険で補填された金額があれば、その分も計算に含まれるため注意しましょう。
- 医療費控除額=(年間の医療費総額-保険金などで補てんされた金額)- 10万円(または総所得金額の5%。いずれか少ない方)
例えば、年間の医療費総額が30万円、保険金などの補てんが5万円、総所得金額が400万円の場合、控除額は以下のようになります。
- (30万円-5万円)-10万円=15万円
この場合、15万円が医療費控除の対象額です。
還付金の目安
還付される所得税額は、医療費控除額に所得税率を掛けた金額になります。
所得税率は課税所得に応じて異なりますが、例えば課税所得が330万円を超え695万円以下の場合、税率は20%です。
例えば、医療費控除額が15万円で所得税率が20%の場合、還付される所得税額は以下のように計算できます。
- 15万円×20%= 3万円
また、医療費控除は住民税にも適用され、住民税率は一律10%です。同様に計算すると、住民税の減額分は以下のようになります。
- 15万円×10%=1万5,000円
したがって、所得税と住民税を合わせて、合計4万5,000円の税負担軽減が期待できます。
まとめ
インプラント治療は高額になることが多い治療ですが、医療費控除の対象になるケースもあるため、税金が軽減される可能性があります。
医療費控除は確定申告のみで申請が可能になっており、年末調整では対応できません。手間がかかると感じられるかもしれませんが、その分、所得税や住民税の負担が軽減されます。
審美目的のインプラント治療は医療費控除の対象外ですが、噛む機能を回復させるための治療法としてであれば対象になる可能性が高いため、ぜひ申告してみてください。
福山デンタルクリニックでは、インプラント治療についてもご相談いただけます。医療費控除の対象になるかどうかなど、気になる場合にはお気軽にお問い合わせください。