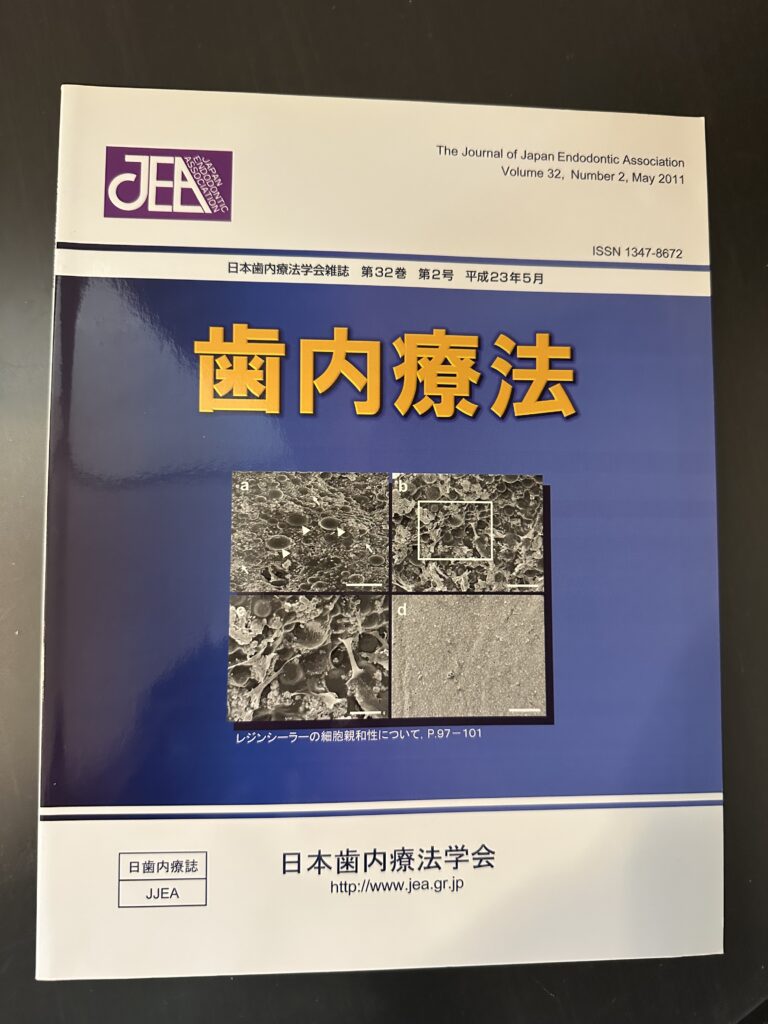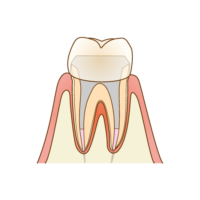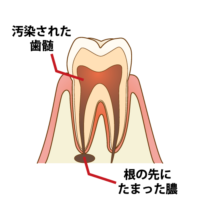歯内療法に関連した非歯原性歯痛の一例 という論文
「歯が痛いから歯医者に行ったのに、歯医者では何も無いと言われた」そんな経験をされた方が時々来院されます。 実は、「非歯原性疼痛」というケースがあるのです。また、非歯原性だけども、歯の治療がトリガーになるケースはあります。
今回は、平成23年5月に日本歯内療法学会誌に掲載された、65歳女性の非歯原性疼痛の一例をもとに紹介していきます。
症例紹介:65歳女性の非歯原性疼痛の一例
患者:65歳 女性
主訴:左上顎前歯から小臼歯部にかけての歯肉に、ジリジリとした持続的な痛み
現病歴
患者は、左上顎前歯から小臼歯部の歯肉にかけて「ジリジリとした痛み」を自覚し、近隣の歯科医院を受診した。数ヶ月にわたって治療を受けたが症状は改善せず、1日に数回疼痛が出現するため、日に何度も歯科医院を受診することがあった。
その後、痛みが一時的に軽減したため根管充填が行われたが、再び痛みが出現。より専門的な診断と治療を求めて、大学病院(日本大学)を受診した。
日本大学での治療:左側顔面部全体に非拍動性の持続性鈍痛および違和感があった。原因となる歯を探すために叩いて診断するのには反応はなかった。割り箸を噛んでもらったところ、左上側切歯と犬歯が顕著であった。
治療経緯:舌に圧痕がみられたので筋・筋膜痛症候群を疑診した。関連部位の筋肉を圧刺激すると関連痛がでた。トリガーポイントの存在を確認した。
患者本人に噛み癖を認識してもらい、すなわち「自分は噛み癖がある。日中無意識に上下の歯を接触させている」という意識を持ってもらい、この疾患への理解及び治療への協力を求めた。食いしばりへの認知行動療法として「くいしばり日記」をつけてもらった。
また、同時にマッサージも行ってもらうようにした。
症状が軽減してきたので、根管充填を行った。2ヶ月後の時点では良好な予後を示した。
考察
1.歯の治療がトリガーとなり筋・筋膜痛により誘発された中枢性感作を介し、逆構成に左側顔面部に痛みが発現した。
解説すると次のとおりです。
まず、歯の治療がきっかけとなって、顎のまわりの筋肉(たとえば咀嚼筋)に負担がかかり、筋肉のこわばりや炎症によって痛みが出た可能性があります。これを「筋・筋膜痛」といいます。
さらに、こうした筋肉由来の痛みが長く続くと、**脳や脊髄が過敏になり、痛みに敏感な状態(中枢性感作)**になることがあります。すると、もともとの痛みの場所とは違う場所にも痛みを感じるようになります。
この症例では、本来は右側の歯に関連する治療から始まったにもかかわらず、反対側の左の顔の一部にまで痛みが広がってしまったという点が特徴です。これは、脳や神経の働きによって、痛みの感じ方が変化した結果と考えられます。
2.原因特定できない歯痛においては、口腔顔面痛とくに「非歯原性歯痛」といった概念を踏まえた多面的な対応を奨励することが重要
感想
日常診療において、原因不明の痛みに遭遇することがあります。その場合、視診やレントゲンによる診断で何も無い場合のみ「非歯原性歯痛」と考えて診断にはいります。最後の最後の診断です。原因が目に見えないのは治療する側にもリスクがあります。できるだけ、保存的な方法からアプローチします。治療が後手後手になってしまうのは、最初から、ご了承ください。できるだけ、患者に寄り添った治療をしたいと思えるような論文でした。なお、治療期間について述べられてないのが気になりました。2年くらいかかったのかもしれません。